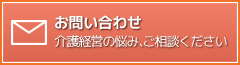加藤厚労相は、4月7日のテレビ番組で標記について、次のように語りました。「医療、介護、年金などで保険料を頂いているが、医療は医療、年金は年金に使うという制度の目的がある。例えば年金や医療のお金を子供にもっていく、という余地は正直に言ってない。今でも医療などでは保険料を上げていかざるを得ない状況である。」
岸田首相が掲げる異次元の少子化対策は、財源の確保が最大の課題です。自民党内ではその手立てをめぐり、医療や介護、年金などの保険料の一部を達洋する案が出ていた経緯があります。
加藤厚労相は続けて、「新たな社会保険の方式で負担していくのか、税財源で負担していくのか、これからやるべき施策も含めてよく議論していきたい。」と述べました。